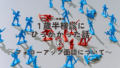1歳半検診について調べると「発達障害」と出てきて不安になりますよね。
私もその1人でした。
1歳7か月の時に市町村が実施する1歳半検診がありましたが、見事ひっかかりました、、、
2歳になる半年後に面談と言われました。
そして先日2歳の面談でしたが、結果は「2歳半での面談は不要、電話で様子を確認します。」
とのことでした。
2歳の面談の内容については後日記載したいと思いますが、
今回は1歳半検診の内容と、その時の成長具合、検診後に取り組んだことを紹介します。
本記事では以下の疑問を解消します
- 1歳半検診の内容は?
- 引っかかったら?
- まだ話さないからやばい?
- まだ歩かないとだめ?
- どんな対策をすればいい?
1歳半検診とは?
子どもの成長や発達を評価するための重要な検診です。
身体の発育、運動能力、言語能力、社会性、感情面などをチェックします。
医師や保健師、心理士が立ち会っているので育児で困っていることや悩みを相談することができます。
1歳半検診に引っかかるとどうなる?
成長や発達の面で何らかの遅れや問題が見られた場合、以下のような対応がなされます。
- 再評価
引っかかった項目について、再度詳しく評価されることがあります。別の日に再検査が行われることもあります。
- 専門家への紹介
必要に応じて、小児科医や発達支援専門家、言語聴覚士などの専門家への紹介が行われることがあります。
- 療育や支援
発達に遅れがある場合、早期の療育や支援を受けることで、適切な成長を促すためのプランが提案されることがあります。
- 保護者への情報提供
どのような支援が可能か、具体的な対策やアドバイスが提供されます。
- 経過観察
問題が軽微な場合は、定期的に経過を観察し、次回の検診で再評価することもあります。
検診で何か気になる結果が出た場合でも、早期に対応することで、子どもの成長をサポートすることが可能と言われています。
1歳半検診の内容は?(神戸市の場合)
うちの子が受けた1歳半検診の内容は以下の通りです。
・発達状態についてのアンケートを事前に記入する
・身長、体重、胸囲の測定
・歯科検診(希望者はフッ素塗布もあり)
・小児科医の問診
・積み木が3つ以上詰めるか、紙に書かれた絵を理解して単語を発するかのチェック
・保健師への相談
神戸市の場合は、積み木、発語、指差しのチェックがありました。
積み木は想像していたものと違いました。
約2cm×2cmの小さい積み木(色は赤のみでシンプルなもの)を3つ以上詰めることがクリアの条件でしたが、うちの子はその場に委縮してやりたがらず1つも積むことができずクリアならず、、、
やれ、と言われるとやりたくないタイプのようです(笑)
誰に似たんだか、、、(たぶん私です(笑))
積み木をする場所も床に積み木があって積んでいくのかと思っていましたが、会議用の机が用意されていてそこで積み木を詰め!という状態でした。
椅子も大人用なので保護者の膝の上に座らしてしないといけなく、なかなか集中しづらい環境でした、、、
あまり子供に配慮していない環境だな、と感じました。
それでもほかの子はできたでしょうけど、、、、
積み木は保育園では問題なくやっている聞いているのであまり心配していません。
指差しについては、家でもしたことがなかったので無理だろうな、と思っていましたが案の定イヤイヤで答えませんでした。
また保健師に育児で悩んでいることや困っていることをする機会があり、うちの子は指吸いがまだ続いていたので相談しました。
指差ししない、積み木をしない、指吸い、ということで心理士と相談して帰りますか?と提案され、心理士と面談しました。
1歳半検診時(1歳8か月)の発達状況
うちの子の検診時の状況を簡単にまとめます。
- 運動面:歩行あり、段差上り下りできる
- やわらかいクッション型のブロックを積んで遊ぶ
- 生活面:コップのみできる、スプーンが使える、ご飯を食べ終わると手を合わす
- 指差しなし→ほしいものを取ってもらいたいときはママの手をほしいものに持っていくといったクレーン行動あり
- 言語面:1~3語(ティービー→テレビ、こっこ→ごはん)など
- その他バックグラウンド:保育園に通い始めて1か月くらい、指吸い大好き
指差しをせずにパパママの手を取って自分の欲しいものに連れていく、という行動があり、調べると「クレーン行動」というものがヒットしました。
どうもクレーン行動は自閉症の子供の特長のひとつだとか、、、
かなり焦りました、、、
でもこう書いている記事もありました。
クレーン現象があれば必ず自閉症である」というわけではないということです。確かにクレーン現象は自閉症児によく見られる行動ですが、健常児に現れることもよくあるからです。
健常児でも言葉をしゃべり始める1歳~2歳頃の間は、自分の意思表示が上手にできず、他人の手を使います。そのため、言葉や指差しで自分の気持ちを伝え始める前に、ママやパパの手を引っ張っていくクレーン現象が見られることがあります。
私は「話始める前では健常児でも見られる、、、」
この言葉を信じて無理に指差しをさせたり、「言葉で話して!」などと言わないように我慢しました、、、
(児童館に来ていた保健師さんに相談したときに「無理に話すよう強く言わないでください」とアドバイスをもらっていました。)
心理士との面談内容(1歳半検診時)
まず、心理士との面談でも積み木と指差しのチェックをされました。
でもやっぱりうちの子はやりませんでした(笑)
保育園では積み木していると伝えたり、レゴ好きで積んでいるという話もしましたがレゴはハメやすい形状だから積み木とはまた違うかな~とOKにはなりませんでした。
指吸いについて対応策(暇にならないように手先を使う遊びをする、お気に入りのものを持たせるなど)を教えてもらいました。
その後いろいろと質問されました。
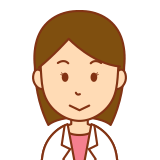
「おむつをゴミ箱に捨ててきて~と言ったら捨てますか?」

頼んだことがないのでわかりません
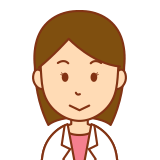
う~ん、、、(困)
後々調べるとこれもチェック項目なんですね(笑)
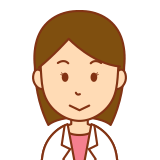
ママ、パパは言わない?

「まぁ!」と言っているけどそれがママとはっきり認識しているかわからないです
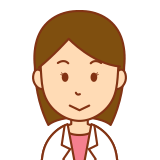
う~ん、、、(困)
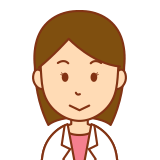
1歳半の時点で単語が3つほど発語があるのが大体の目安です。
たんめんさんの子は3つないのでまた半年後の2歳になった頃に面談しましょう。
半年後の○月×日△時からで予約入れておきますね、

はい、、、、
といった流れでした。
これって引っかかったってこと?とショックを受けながらも了承しました、、、
言葉もブーブーやまんま、パパ、ママなど教科書的な言葉が出ていないので心理士的にはアウトだったようです。
別にテレビでもよくない?と思いましたが、、、(笑)
(うちの子が言っていた単語はティービー→テレビ、こっこ→ごはんの2つ程度でアウトでした。)
子どももいつもと違う雰囲気、知らない人に色々話されることがストレスだったようでずっとぐずぐず、指を吸っていました、、、
(半年後の面談時にずっと指を吸っていたからそれも気になっていた、と言われました)
心理士面談の感想
心理士の方は発達状況を見るため基準に合わせて判断されます。
正直マニュアルに合わないものは×になる感じで杓子定規な判断です。
家や保育園でできていると話しても、「そうなんですね~」といった感じで参考にする程度で、実際に確認できなければ×と判断される感じがしました。
まぁ心理士さんからすればできている確証を得ていないのに無責任にダイジョブ!とは言えない立場なのも理解できます(笑)
心理士さんは日常生活や個人の性格を鑑みて判断するわけじゃないので、
パパママが育てにくさを感じていなかったり、保育士さんから何か気になることを言われていないので、そこまで結果を気にしなくてもいいだろうと前向きに考えるようにしていましたが、でもやっぱりショックでした、、、
あまり気にせず、、、でも言葉が出ることを願っていました!(笑)
1歳半検診後の様子
1歳半検診終わってから1週間くらいで、急にママ!パパ!というようになりました。
ほんと一安心しました、、、(笑)
1歳9か月ごろになると、名前を呼ばれたら「はーい!」と腕を上げて返事するようになりました。
これは完全に保育園効果ですね!
次に覚えたのは「おいちー」でした。
ごはんが大好きなうちの子らしいなと思いました(笑)
テレビ、ママ、パパ、美味しい、、、と明らかに好きなものから順に覚えていて本当に面白いですよね。
指差しについて
実は1歳半検診に備えて100均でどうぶつずかんの絵本があったのでそれを買って指差しの練習をしていました。
しかし全く興味がなく効果ありませんでした。
そのまま1歳半検診を迎え、散々な結果だったのですが、その後子どものフォトブックを絵本と一緒においているとフォトブックに興味津々!
一緒に写真を指差しながら見て、これはママ、これはパパ、これは○○ちゃんだね、△△してるねと話していました。
すると自分が指さしたものにママが反応するという仕組みを理解し、楽しい!と感じたようで、指差しをするようになりました!
写真に義実家で飼っている犬が写っていて、わんわん!と言うようになり、買い物に行ったときにペット用品(犬や猫の画像があるもの)を指差し「わんわん!」や「にゃーにゃー」と指差しするようになりました。
それが大体1歳9~10か月くらいの時です。
その後、こどもちゃれんじプチでもらったことば図鑑やお風呂ポスターに興味を持ちはじめ、
ライオン→ガオー、牛→モーモー、羊→メーメー、アヒル→グワッグワッ
など言うようになりました。それが大体1歳10~11か月頃でした。
たまに赤ちゃん言葉は教えない方がいい、といった情報が見聞きすることがありますが、うちの子の場合、赤ちゃん言葉だったから吸収された感は否めません。
無理に大人の言葉を教えるより覚えやすいものを教えた方がいいような気がします。
おすすめの1歳半検診対策
youtubeを減らす
これは私の反省点です。
1歳過ぎで体力もついてきて動き回るし、でも言葉や物事の理解が乏しくイヤイヤがひどい時期で私はすごく疲弊してyoutubeに頼ってしまっていました、、、
youtubeを見ていると機嫌よく、消すと怒るからまた見せる、、、といった悪循環でした。
1歳半検診後はyoutubeを減らす努力をしました。(0ではありません(笑))
テレビのオフタイマーを使って30分で1度テレビが消えるようにしていました。
私が消すと怒りますが勝手に消えた場合は、意外とすんなり受け入れて別の遊びをするようになったのでオフタイマー機能はおすすめです!
しばらくするとまたテレビ~!ということもありますがその時は「ちょっと目を休ませよう」といって違う遊びをするようにしています。
そろそろ限界かなと感じたらまたつけて、30分で消えるようにしたり、パパが見たいもの(子供は興味ないもの)を見たりして少しずつ我慢できるように促しています。
泣かれることもありますが、兄弟姉妹がいればいつも自分が見たいものが見れるとは限らないのでその状況をパパママで作っている、と思えば罪悪感が減ります(笑)
絵本を読む
これはよく言われるやつですが、ことば図鑑など言葉を覚える系の絵本は、そもそも興味がなかったのですぐあきらめたのですが、もう少し粘っていろいろ試せばよかった、、、と後悔しています。
今2歳で少しずつ言葉が増えてきているのですが、最近のお気に入りは腹ペコあおむしのあいうえおカードです。
プレゼントで貰い、これ使うかな?と思いましたがまさかのヒット!
カードをめくるのが楽しいみたいで図鑑より興味を引いたみたいです!
図鑑がいまいちハマっていない子はぜひ試してほしいです!
最近インスタでよく見る、あかちゃんごおしゃべりえほん。
もっと早く知っていたら買ったのに~!と後悔しています(笑)
確かにうちの子が覚えた言葉順に載っているのでいいのでは!?と思っています。
積み木で遊ぶ
できれば小さくてシンプルな積み木がいいかもしれないです。
検診では約2cm四方で赤色の積み木でした。
サイズ感のイメージはこんな感じです。
検診ではカラフルではなくこの赤色だけ、って感じでした。
フォトブックで指差し
指差しをしない子にはフォトブックはおすすめです。
子どもって自分の動画を見たりするのが好きだったりするので、興味を持ちやすいのではないかと思います。
背景に映っているものを話したり思い出を話したりすると喜ぶと思います。
好きな絵本など興味の持っているものがあればそれで指差しをしながら読んであげるのもよさそうですね!
指さしたものに大人が反応してくれるということを理解すれば指差しするようになるんだと思いました。
できることに目を向ける
1歳半検診での項目はあくまで目安です。
できないことがあってもほかにできていることがあればそれでいいと思います(笑)
うちの子も言葉は全然でしたが、運動面は進んでいたので
「運動が好きなんだな~スポーツ選手になるかな?」というように考えていました
完全に親バカですが、パパママくらい親バカでいいかなと思います!(笑)
私の友人の子供は4カ月で10キロを超えるビッグベビーだったので歩くのが遅く、1歳7か月頃だったそうです。
検診時は歩いてなくて引っかかったそうですが時期が来れば歩くようになります。
友人は、歩かない分、脳に刺激を与えよう!といろんな絵本やおもちゃを試したそうです(笑)
個人のペースがあるので焦らず見守ることが大事だなと感じます。
できることを伸ばしつつ、できないことにはどうやったら興味を持つかな?と考えるのがいいかもしれないですね!
まとめ
今回は1歳半検診について私の体験談を紹介しました。
何度も言いますが、1歳半検診の基準はあくまで目安だということを忘れないでほしいです(笑)
個人のペースがあるのでそこから外れたらダメだ、というわけではないと思います。
最近は「発達障害」ビジネスでもあるのかな?と思うくらい「発達障害」というワードがすぐでてきますよね。
製薬会社や知育おもちゃメーカーなどの戦略のように思えて仕方ありません(笑)
興味の有無や得意不得意など個人差があるということを理解しないといけないと思います。
うちの子も今後どういう結果になるかわかりませんが、現時点では言葉が増えてきているので焦らずに子供のペースに合わせて成長を見守りたいと思っています。
でも検診に向けてできることはやりたい!という親心もわかります!
今回の記事で紹介した内容をぜひ参考にして色々試してみてください!!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/412a6641.9ab4bf4f.412a6642.af7d9b93/?me_id=1213310&item_id=21305871&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9246%2F9784330019246_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/412a6641.9ab4bf4f.412a6642.af7d9b93/?me_id=1213310&item_id=18440319&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2735%2F9784074222735.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/412a7d2a.2cf40b51.412a7d2b.e952b0b9/?me_id=1364802&item_id=10616932&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fohstore%2Fcabinet%2F0067%2F2bjf2p9d8u_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)